あなたは、人から理解されていますか?
あなたの言葉や気持ちは、相手に届いていますか?
あなたが考えている自分の内面と、他人が受け取っているあなたは同じでしょうか?
他人があなたを理解できないのと同じく、あなたも他人を理解していません。
本当のあなたを理解してもらいたいなら、まずは、あなたが他人を理解しなければイケません。
 kou
kouGive & Takeです。
Giveが先です。
私達は、ある程度親しい仲と感じている時、「言わなくてもわかる」「相手も同じ」と勝手な解釈が入ります。
確かに、そうような場面もあります。
少なからずあるから誤解するのです
しかし、この前提でのコミュニケーションは、暗礁に乗り上げることが多く欲しい結果までたどり着けない。
気持ちの良いコミュニケーションには、「相互理解」が必要なのです。
『7つの習慣』【第五の習慣】「まず理解に徹し、それから理解される」の理解
なぜ理解することが最初なのか
日々の生活での使い方
コミュニケーションの変化
*著者の経験からの解釈・意見も散見します。
まず理解する
あなたは、相手の話をちゃんと聞いていますか?
途中でさえぎり、自分の話を打ち込んでいませんか?
「自分は、昔あーだった」「その時は、こーだった」
自分のことを気持ちよく話すことが多くはないでしょうか?
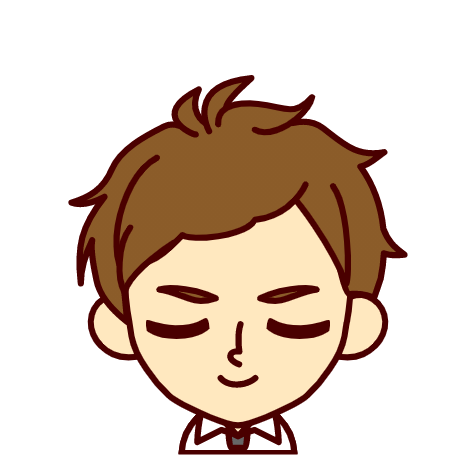
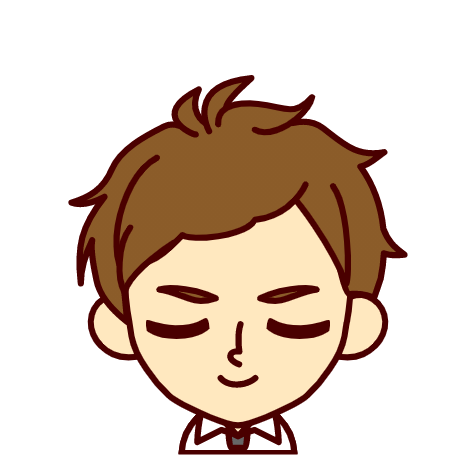
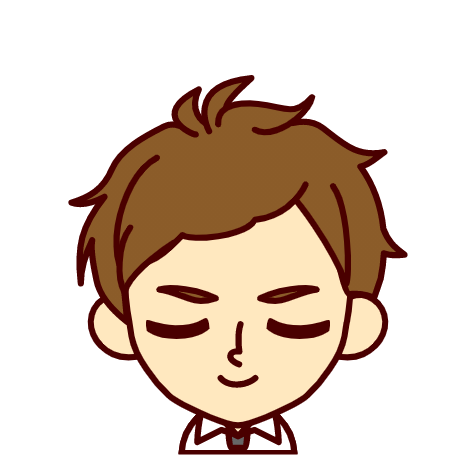
まずは、自分の意見や昔話を挟まずに聞いてあげましょう。
よく言われる、「口は一つ、耳は二つ、だから、話すよりも2倍人の話を聞きましょう」がここでも当てはまります。
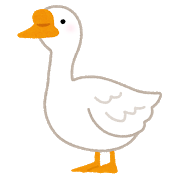
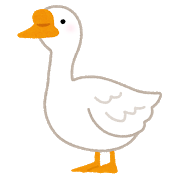
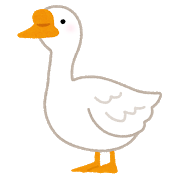
だけど、学校では「話す」ことは習っても「聞く」ことは習わないよね?何で?
相手が妻・夫、友人、同僚・上司などなんであれ、相手に影響を与えるには、まず相手を理解しなければならない。
そして、本心を打ち明けられるには、あなたの人格が「誠実」であることです。
あなたが誠実であれば、相手と信頼関係を築き、信頼残高を積み上げることができる。
あなたの人格は、常に誠実さの度合いを周囲に発しており、その場限りで取り繕うことはできません。
たとえ、表面は取り繕ったとしても、それは懐柔だと判断され相手はさらに警戒するでしょう。
「理解してから理解される」ことには、大きなパラダイム転換が必要である。話をしているとき、ほとんどの人は、理解しようとして聞いているのではなく、答えようとして聞いているのだ。
スティーブン・R・コビィー著『7つの習慣』より
話しているか、話す準備をしているのか、二つにひとつである。
理解するための聞き方
私達の普段の聞き方は、無意識に次のような段階に分けている。
- 無視する
- 聞くふりをする(空返事、もしくは相づちだけ)
- 選択的に聞く(基本は聞き流し)
- 注意して聞く
本当に相手のことを理解するには、さらに上の「感情移入の傾聴」が必要である。
そして、この感情移入の傾聴をすることは、信頼残高への預け入れに繋がります。
感情移入には、相手の見地に立ち、相手のパラダイムで物事を五感を使って感じとることが必要です。
当記事は、スティーブン・R・コビィー著『7つの習慣』を各習慣ごと・重要部分別に噛み砕いてお伝えしてます。
『7つの習慣』は、累計発行部数が全世界4000万部の大ベストセラーで、日本国内だけでも240万部突破している自己啓発の名著。
また、平均年収974万円の30代以上が推薦する「新社会人に贈りたい本」にも選出されています。
分厚く読み応えのある紙の本から学べば満足感もひとしおですが、オーディオブックならば片手間に何度も聞き流すことができ、移動中の時間も無駄にしません。
自叙伝的な聞き方
引用文にあるように、私達は「答えようとして」聞いています。
それが、この自叙伝による四つの反応になって現れます。
評価する
賛成、もしくは反対する。
自叙伝に照らし合わせて、「自分なら」という立場で答える。
悪気はないが、相手の立場に立っていない。
探る
自分の視点で質問する。
情報の物足りなさを感じている。
自分が答えやすい誘導的な質問になることがある。
助言する
自分の経験に基づき、助言やアドバイスを与える。
自分のパラダイムと自叙伝が基になっており、内容の適格性に当たり外れがある。
解釈する
自分を基準にして、相手の動機や行動を解釈してしまう。
自分の自叙伝やパラダイム、見聞きしたことが上限になってしまう。
感情移入の傾聴
前項で紹介した「理解するための聞き方」の最上位に感情移入の傾聴がある。
この感情移入の傾聴を身につけることの意義を考えて欲しい。
それは、コミュニケーションの有意義で即効性がある劇的な改善をもたらすことだ。
習得するには四つの段階がある。
これは一般的な傾聴です。
単なるオウム返しですが、「聞いている」ということが相手に伝わるだけです。
例)
相手 :今日、見た映画は面白かったよ。
あなた:そうか、面白かったんだね。
言葉を表面で捉えているだけで、まだ感情は入っていない。
例)
相手 :今日、見た映画は面白かったよ。
あなた:面白い映画だったんだね。
話し手の感情に焦点を置く。
例)
相手 :今日、見た映画は面白かったよ。
あなた:何だかワクワクしているね。
ステップ2と3の組合わせを行う。
例)
相手 :今日、見た映画は面白かったよ。
あなた:面白い映画を見て、とってもワクワクしているね。
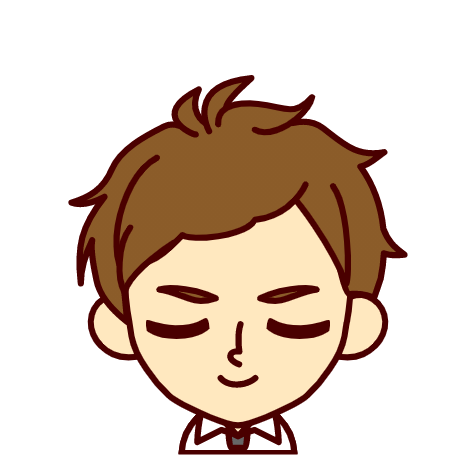
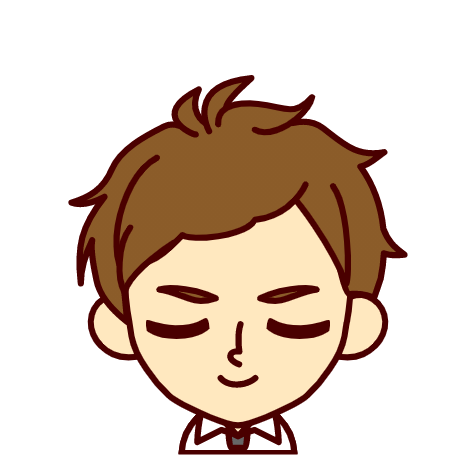
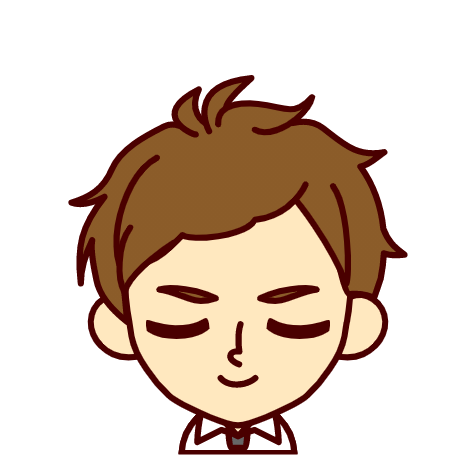
感情移入の傾聴ができるようになると、相手はあなたに「無垢な内面」を見せ始めます。
信頼残高の大いなる積み上げです。



本当の理解と大いなる信頼がなければ、あなたがどれほど正しく立派なことを話しても、相手の心(耳)には届きません
上辺だけの接し方だと相手には直ぐにバレます。
相手が内面を見せるときは、あなたは敬意を払わなけばイケない。
感情移入の傾聴は、テクニックではありません。
あなたの内面と相手の内面の繋がりであって、時には言葉もいらず、話を聞いて抱きしめるだけでも誠意は伝わります。
人は理解されたい。だから、理解することにどんな大きな時間の投資をしても、必ずそれを上回る時間の回収ができる。
スティーブン・R・コビィー著『7つの習慣』より
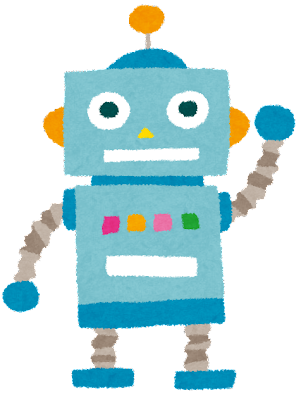
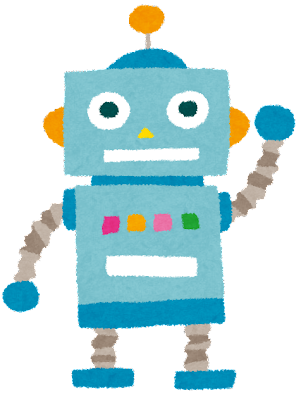
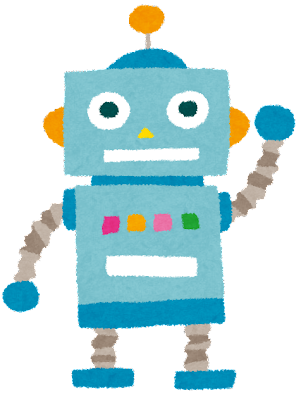
自分自身を理解するためには、自身の可能性を信じることが必要。
この挑戦が飛躍のチャンスになるかも?
理解とWin-Win
相手を理解すればするほど、自分とのモノの見方であるパラダイムが大きく違うことに気がつく。
しかし、私達は自分のパラダイムが「正しい」と考え、意識せずに人に押してけている。
【第四の習慣】で学んだ他者との関係では、Win-Winが最善であった。
そのWin-Winを導くには、「理解する」ことが欠かせない。
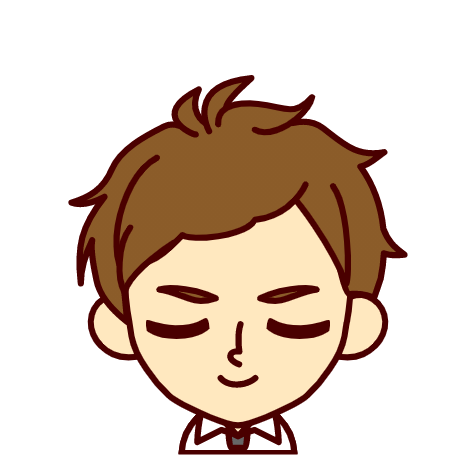
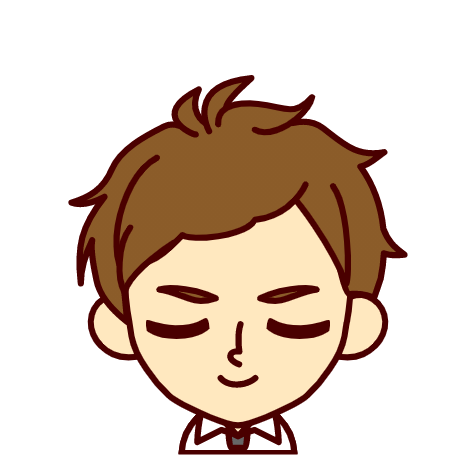
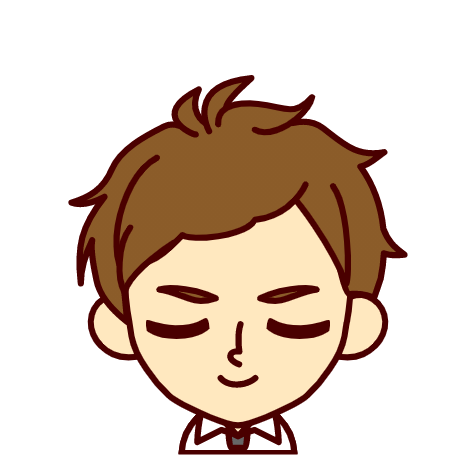
「理解する」ことが、コミュニケーションの鍵です。
相手に求めるのではなく、先にあなたが理解を示さなくてならない。
高い人格が必要ですね。
理解される
あなたは理解を示しました。
次はあなたが理解される番です。
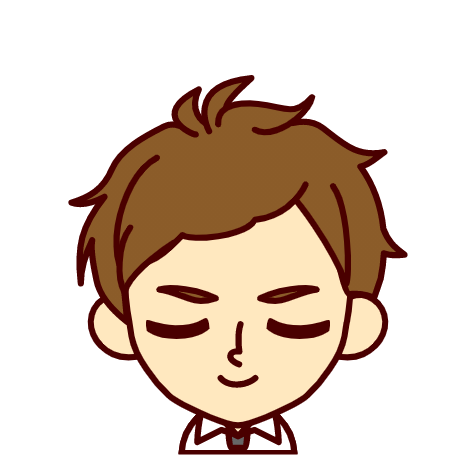
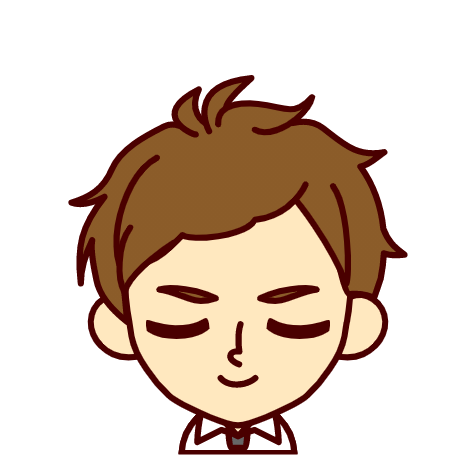
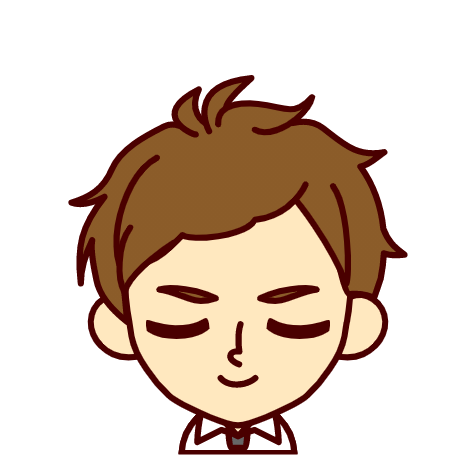
理解するには「思いやり」が必要です。
理解されることを求めるには「勇気」が必要です。
効果的なプレゼンテーション
昔のギリシャのエトス・パトス・ロゴスという哲学が『7つの習慣』の本文に紹介されています。
これは順番も大事で、人格、人間関係、プレゼンテーションの論理展開の順番になっています。
エトス
個人に対する信頼性。
『7つの習慣』流に言えば信頼残高に当たります。
パトス
感情移入のことです。
相手の不安や関心事に理解を示し、相手の立場になって感じること。
ロゴス
理論であり、プレゼンテーションの論理展開です。
相手のパラダイムや不安、あるいは関心事に対する正しい理解を踏まえて、自分の考えを、明確に、具体的に、ビジュアルに、相手に向かってプレゼンテーションすると、こちらの考えの信憑性は著しく高まる。
スティーブン・R・コビィー著『7つの習慣』より



私の理解では、以下のようになります。
(間違えていれば教えて下さい)
[エトス]信頼している相手が話す機会を作ってくれた。
[パトス]自分の不安事の徹底的な理解と感情移入の傾聴を受けた。
[ロゴス]誠意を感じ、理路整然とした話の内容に興味を抱き、双方の意見を組み合わせればもっといい解決案になると確信を持てた。
\ 遊びながら学べるよ /



わかりやすいですよ!
7つの習慣
この記事は、スティーブン・R・コビィー著『7つの習慣』を参考にしております。
- 累計発行部数が全世界4000万部の大ベストセラーで、日本国内だけでも240万部突破
- 平均年収974万円の30代以上が推薦する「新社会人に贈りたい本」に選出
- 鉄板のビジネス書として、長く親しまれている名著
kou2(筆者)が自己流に噛み砕いて、特に読者の方に知っていただきたいことを抽出してご紹介いたします。
『7つの習慣』では、 依存 → 自立 → 相互依存 への成長にあなたを導きます。
読者は、自らの価値観を明らかにして各段階ごとの成功原則を学びます。
その結果、内面から変化を起こし人格を高めることで、人生の充実を経験する自己変革を成し遂げていくのです。
もし、この記事で『7つの習慣』に興味をお持ちになり、自身との共通点を感じられた方、もっと深く学びたい方はぜひ名著『7つの習慣』を手に取りお読みください。
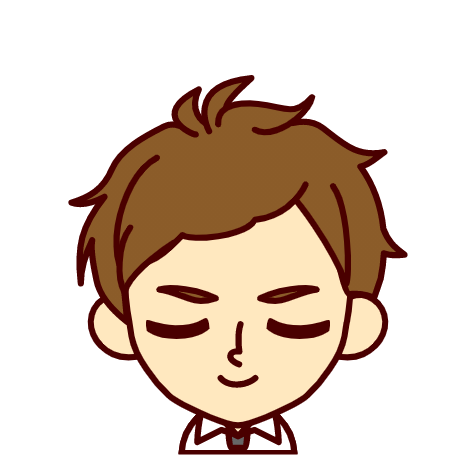
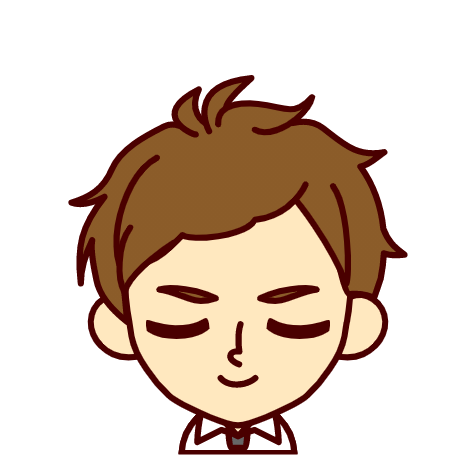
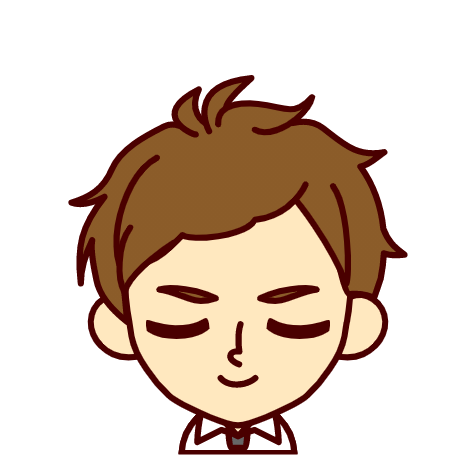
今まで考えていたこと・悩んでいたことの原因と解決案が書かれています(体験談)
あなたも是非読んでみることをお勧めします。
きっと座右の書に加わることでしょう。
『7つの習慣』では、相互依存の状態を目指しており、そこに至るためにいくつもの原則が紹介されています。
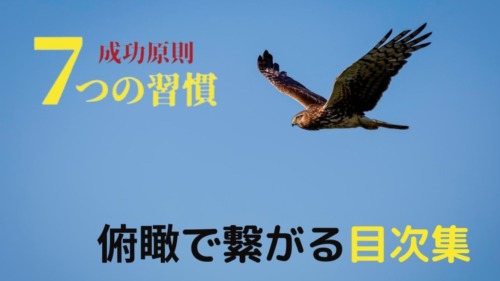
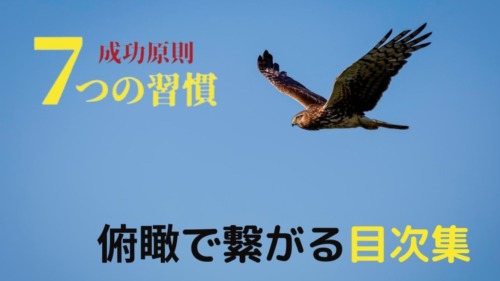
以降の記事では、【第五の習慣】に記載されている重要なエッセンスをご紹介しています。
オーディオブック配信サービス – audiobook.jp
【第五の習慣】傾聴まとめ
【第五の習慣】は、あなたの影響の輪の中心にあります。
それは、あなたがコントーロールできる事柄であり、信頼残高を築き上げ、一緒に効果的な人間関係をつくる機会なのです。
自分の自叙伝を話したい欲求に駆られるだろう。
しかし、それは良好な人間関係を作ってからのお楽しみにとっておきましょう。
私も崩れてしまった人間感に悩まされています。
相手のことを切り捨てることができるならこれ以上悩まなくても済みます。
しかし、それはできません。
私は、相手の力を必要としているし、良好な人間関係で得られる大いなる成果を知っているからです。
大切な人のために使う時間は無駄にはなりません。
私は、誠実さを持って相手を理解し、相手に理解されるのを待とうと考えています。
人間関係が破綻するのを防ぐためにも、また、破綻の改善のためにも【第五の習慣】を当てはめて良好な人間関係を構築していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
\ 我が家宝 /


コメント